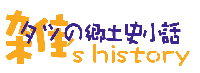ある民衆史家の死
獨協大学経済学部教授斎藤博先生が10月17日亡くなられた。先生のゼミの卒業生のKさんからの訃報に接したのは11月末のことであった。 先生の家系はお父上の代まで槻木町にお住まいだった。したがって、柴田町内には多くのご親戚がいらっしゃる。柴田町は先生にとっての、いわば父祖の地である。そのこともあって、先生にはiカンパニーのメンバーに加わっていただいた。 しかし、先生と柴田町との関わりはそれだけに留まらない。 何歳の時であったか、何年の事であったか、お聞きする機会はなかったが、先生と柴田町との関わりについて、斎藤ゼミに語り継がれている伝説がある。 30代の初め、昭和40年代のごく初めの事と思われる。ご親戚のつてを頼ってであったか、柴田町役場に資料採訪に来町されたときの事である。役場の駐車場に古紙業者のトラックが駐車しており、和紙の束を積み込む作業の真っ最中であった。先生は問答無用、和紙の束を庁舎内に戻させたというものである。 これが、伝説ではなく事実であることを私は確認している。私が柴田町の職員として町史の編纂の仕事に就いた年、庁舎は新築され大量の廃棄文書が旧庁舎の最も広い会議室に山積みされた。私はそのなかから、編纂に必要と思われる文書を選びだす作業にあたった。その文書に大きな段ボール箱(家具調TVが2台入るほどの)に入った文書が加わった。その箱は教委に机を置いたときから部屋の一角に置かれていたものであった。 それが、斎藤先生の武勇伝の賜物であることを知ったのは何年か後のことである。 当時、確か仙台大学の講師をしておられた田島昇氏が役場文書を見たいというような来訪目的であったが、棚に積まれた文書を一瞥しただけで、手を延ばすでもなく、斎藤さんを知っているかと言う。知らないというと、お前さんのとこの資料を使って『近代日本の社会基盤』(1973年 蒼文社)という本を書いたのだ、と教えてくれたのだった。 しかし、私はまだ先生の武勇伝、伝説を知らなかった。 先生が編纂室に見えたのは、獨協百年史の資料採訪のためであった。獨協、つまり獨逸協会と柴田町との関係は、先生によれば柴田意成(柴田倫之助先生御尊父)が明治17年ころに獨逸協会学校に入学したというものである。中途退学したらしい協会に記録はないが、柴田町になにか残っていないか、というのが来訪の目的であった。 武勇伝をうかがったのはこの時のことであったと思う。しかし、先生は武勇伝を話そうとしたのではない。トラックから強引に引き降ろさせた資料を使って書きあげたのが『近代日本の社会基盤』であり、これが近代史の先輩研究者から評価された。民衆史家斎藤博が第一歩を踏み出した、その基礎資料があの和紙の束にあったことを話されたのだった。 その後、編纂の仕事を通して先生からはさまざまな励ましやら御指導を頂戴した。 この春以来、入院加療中であったことを知らなかったため、訃報は晴天の霹靂であった。 12月10日、先生の御遺骨は御両親が眠る藤枝市の富士霊園に納められた。 また、レオというクリスチャン・ネームをもつ先生の御遺骨は分骨されて、四谷の聖イグナチオ教会の地下納骨堂に納められた。訃報を伝えてくれたKさんのお誘いで、同月17日のこの納骨式に参列した。 カソリックの、この教会は私の知る教会と全く趣を異にしていた。広い敷地から道路にまで人々があふれていた。そこはさまざまな民族、さまざまな国籍の人で埋っていた。この、いわば「国際性」は奈良時代の仏教寺院の景観なのではと、場違いな幻想にかられた。 式後、近くで昼食会がもたれた。私が知っている人はいなかった、当然ながら。Kさんの顔も思い出せなかった。 食事をとりながら、参列者の自己紹介が進んだ。 私の番が来て、宮城県の柴田町から来た、というとかすかにオーという声が漏れ、視線が集まるのを感じた。例の武勇伝を紹介すると、それはほとんどの参列者の知るところであった。テーブルの斜め向かいに座った、先生と同世代と思われる女性が、そのお話は先生からうかがったことがあります、と声をかけてくださった。この人は獨協大学のオープン・カレッジの受講生で、先生の歎異抄の講義に参加しておられたという。 この女性のクラスメートが6人おり、高校の同級生が3人、大学の同僚や研究仲間がおり、教え子の皆さんがいた。この人たちが語るエピソードのいくつかには、私も加わっていることに気づいた。もちろん、この人たちと一緒という意味ではない。私がこの人たちと同等にお付合いただいたことを知りえたということである。 斎藤先生にとって、柴田町は単に父祖の地であるだけでなく、研究者としての揺籃の地なのだということを改めて感じると同時に、失ったものの大きさを知った。 |